神社は非特定防火対象物に分類されるケースが多く、その消防設備点検や報告義務は、他の施設と少し異なる取り扱いになる場合があります。
消防法上、神社や寺院は次のように扱われます。
原則的には、非特定防火対象物であって、通常は一般の人が長時間出入りしない建物(例:本殿、社務所など)となります。
例外的に、特定防火対象物となって、祈祷や祭事で多数の一般客が集まる建物、または宿泊施設を併設する場合になります。また、大規模な初詣や祭礼で人が密集する社殿などが、一時的に特定対象物扱いになる場合もあります。これは消防署の判断によります。
そして、神社における消防設備点検の概要としては、
本殿、社務所、授与所などに設置される消火器
重要文化財級の社殿などでは設置が義務付けられることもある自動火災報知機
音響装置や放送設備など(必要に応じて)非常警報設備
漏電火災警報器は木造建築が多いため、設置を求められるケースもあると思います。

神社の場合には、
木造建築で延焼リスクが高いことから、消防署が点検・報告を強く指導する地域も多いですし、「文化財保護法」との関連で、消防署と教育委員会の両方の指導が入る場合もあります。別途の消防・防災対策が求められることある、ということです。
流れとしては、
・管理者(宮司や責任者)が消防設備点検資格者または消防設備士に点検を依頼
・点検実施(6ヶ月ごと・年1回)
・結果を「点検結果報告書」にまとめる
・該当する場合は、所轄消防署へ報告書を提出(3年に1回)
あと大阪市など市町村では 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書がおいています。
https://www.city.osaka.lg.jp/shobo/page/0000595403.html?utm_source=chatgpt.com
神社でも消防点検と聞くと知らなかった方も多いと思いますが、実はお寺なんかでもそうですし、大きなお寺も多いので何かあった時には消防対策できてないと大きな被害にあってしまいます。
そういった危険を回避するために、オーディーイーでは日々業務を頑張っております。





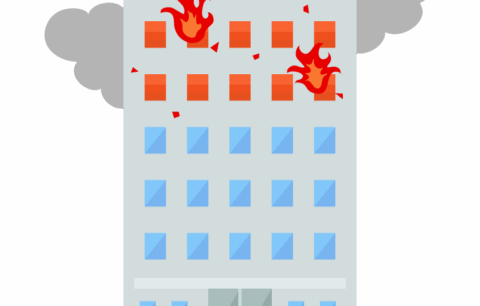







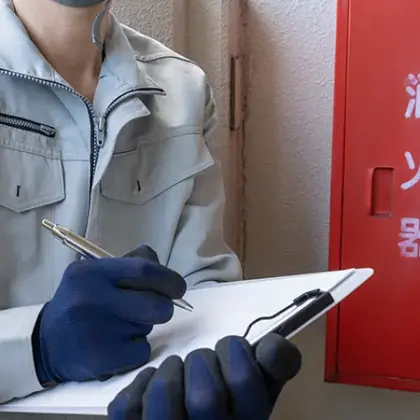

コメント