消防設備士の仕事における「元請け・下請けの割合」や「新築・改修の割合」は、地域・企業規模・業態によってばらつきがあると思いますが、一般論としての業界全体の傾向としておおよその割合をお伝えします。
まず元請けですが、建設会社や施設オーナーと直接契約しますが、大手設備会社や老舗業者が多いのが傾向で、利益率が高いが競争も厳しいのが実際です。
また、下請けですが、元請けの建設会社・設備会社からの依頼で現場作業を担当。中小企業や個人事業主が多く参入していることが多いです。
例えばJRの駅なんかでいえば施設自体はJRで管理していますので、仕事としてはJRの仕事になりますが、建物管理はJRの施設管理会社が担当している、ということが多く、駅の構内の建物や駅ビルになっていればこれもJRで管理、ということもあるので実際には元請けのようで、下請けのようなことも多々あります。
仕事柄で言えば、元請よりも下請けが多いのですがその理由は、ゼネコンや建築会社がプロジェクトを一括請負し、その中の「消防設備部分」を専門業者に依頼する構造になっているためです。
点検業務は比較的元請け契約が取りやすい(施設オーナーと直接契約できる)ため、点検会社の方が元請け比率が高めです。

一方、新築:改修(更新・リニューアル)工事の割合ですがこちらも下請けのほうが多いと思います。日本では建物の新築件数が減少している一方、老朽化した建物の更新需要が増加しているため、改修比率が高いことが理由になります。また、ビルや病院、商業施設などの定期改修に伴う工事は、継続的に発生するため収益源になります。
法定点検や老朽化に伴う改修が中心。火災報知器やスプリンクラーの交換、機器の入替えなどが多いとも言えます。
このような状況かと存じます。
元請けを目指すには信頼と実績が不可欠。技術力だけでなく、営業力や管理能力も問われるので大変だったりします。あと、高齢化建築、消防法の改正による設備更新などから改修工事は今後さらに比重が高まる見込みです。点検業務や保守契約を持つ企業は、改修工事の受注にもつながる「安定収入型のビジネス」が可能とも言えます。
仕事柄大きい建物の仕事になれば下請けになることが多いですし、オーナーさん直接依頼の場合には元請になることもあります。どっちがいいとかはないのですが、お困りごとあればどちらでも任せてもらえるような技術を磨くのが大切かと思います。
弊社は大阪府摂津市を拠点に、防災設備工事・電気設備工事・空調設備を手掛けている会社です。
事業拡大に伴い、消防設備士・電気工事士として一緒に働いてくださる方を募集しております。
弊社は、防災設備工事・電気設備工事などを一貫して手掛けており、付随する工事までトータルで対応できるのが強みです。
高度な消防設備工事といった専門性の高い分野にも対応できるため、多様なスキルを習得し、キャリアアップできる環境です。
働きやすい環境づくりに努めておりますので、ぜひ弊社で一緒に働きませんか?




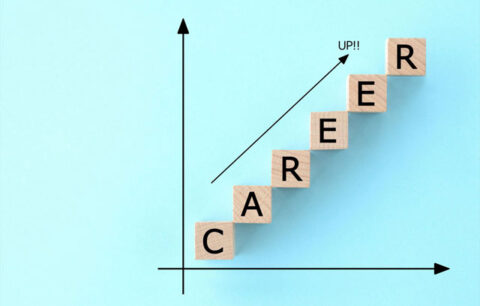










コメント